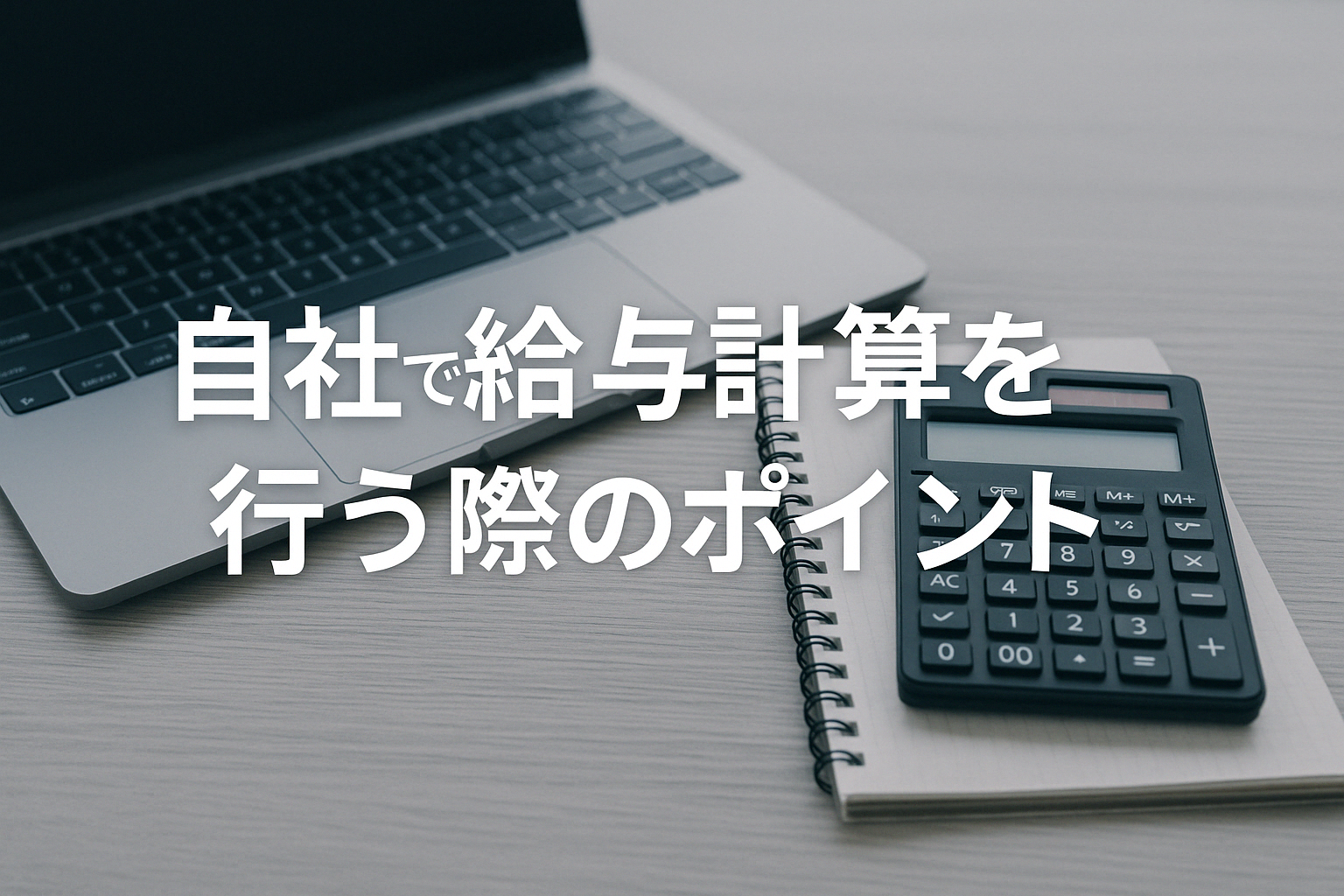
【給与計算の基礎知識】自社で給与計算を行う際のポイントとは?
給与計算は毎月発生する業務でありながら、労務・税務・法改正など幅広い知識が求められる専門性の高い業務です。コスト削減や情報の即時管理といった理由から、自社で給与計算を行っている企業も少なくありません。しかし、業務の特性上「正確性」と「法令遵守」が求められ、少しのミスが従業員の不信感や行政指導につながる可能性もあります。
本コラムでは、給与計算を自社で行う際に押さえておきたいポイントを解説します。
1. 就業規則・賃金規程と整合性をとる
まず重要なのは、給与計算の根拠となる就業規則や賃金規程と実際の運用に齟齬がないか確認することです。例えば、残業代や各種手当の支給条件、支給日や締切日などが規程に明記されている内容と異なっていると、トラブルの原因となります。制度を変更する際は、規程も併せて確認しましょう。
2. 勤怠管理とセットで考える
給与計算は、正確な勤怠データがあってこそ成立します。出勤簿、タイムカード、勤怠アプリなどを活用し、遅刻・早退・残業・有休・欠勤などを正しく把握しましょう。勤怠集計の誤りは、残業代や控除計算のミスに直結します。
3. 社会保険・税金の知識が不可欠
給与には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、所得税などの控除が関わります。これらは毎年の法改正や保険料率の変更により、計算方法や金額が変わるため、最新情報の把握が必須です。誤った控除額で処理すると、従業員にも会社にも不利益が生じる可能性があるため注意が必要です。以下は簡易版ですが、末締め、翌月10日支払いの会社が行う給与計算関連業務の年間スケジュールの例です。
年間給与計算スケジュール
| 月 | 主な業務内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月 | 法定調書の提出・給与支払報告書の提出 | 提出期限:原則1月31日まで |
| 2月 | 昇給の検討、算定 | |
| 3月 | 社会保険料率の改定 | 社会保険料率の変更を給与計算に反映させるタイミングは会社により異なるため注意 |
| 4月 | 昇給、雇用保険料率、労災保険料率の確認、新入社員の社会保険・雇用保険加入手続 | 雇用保険料率の変更を給与計算に反映させるタイミングは会社により異なるため注意 |
| 5月 | 住民税の特別徴収額の更新 | 市町村から住民税の通知が届く時期 |
| 6月 | 労働保険の年度更新の手続き | 提出期限:原則7月10日まで |
| 7月 | 算定基礎届の提出 | 提出期限:原則7月10日まで |
| 8月 | 賞与計算、4月昇給者の随時改定(月額変更)の確認、届け出 | |
| 9月 | 算定基礎届の結果を反映 | 社会保険料率の変更を給与計算に反映させるタイミングは会社により異なるため注意 |
| 10月 | 年末調整対象者の確認・資料収集依頼開始 | 配偶者控除や扶養控除申告書の案内 |
| 11月 | 年末調整準備 | |
| 12月 | 賞与計算、年末調整実施、源泉徴収票の作成開始 | 本年分の給与総額・控除額の確定 |
4. 月額変更届や賞与支払届などの届出にも注意
従業員の給与が変動した際には、月額変更届(随時改定)や賞与支払届など、適切なタイミングで年金事務所等に提出が必要です。届出漏れは行政指導や遡及対応を招く可能性があるため、スケジュール管理も大切です。
5. 専門家との連携も視野に
社内で対応する場合も、社労士や税理士と連携することで、ミスの防止や業務の効率化が図れます。特に「自社で処理したいが制度や法令に自信がない」「属人化していて不安」という場合は、スポット相談やアウトソーシングの検討も有効です。
まとめ
給与計算は「できて当たり前」と思われがちな一方で、非常に繊細な業務です。従業員の信頼を守り、企業のリスクを最小限に抑えるためにも、基本を押さえたうえで、必要に応じて外部の専門家の知見を取り入れることをおすすめします。
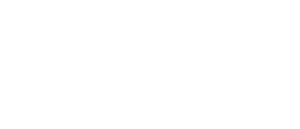
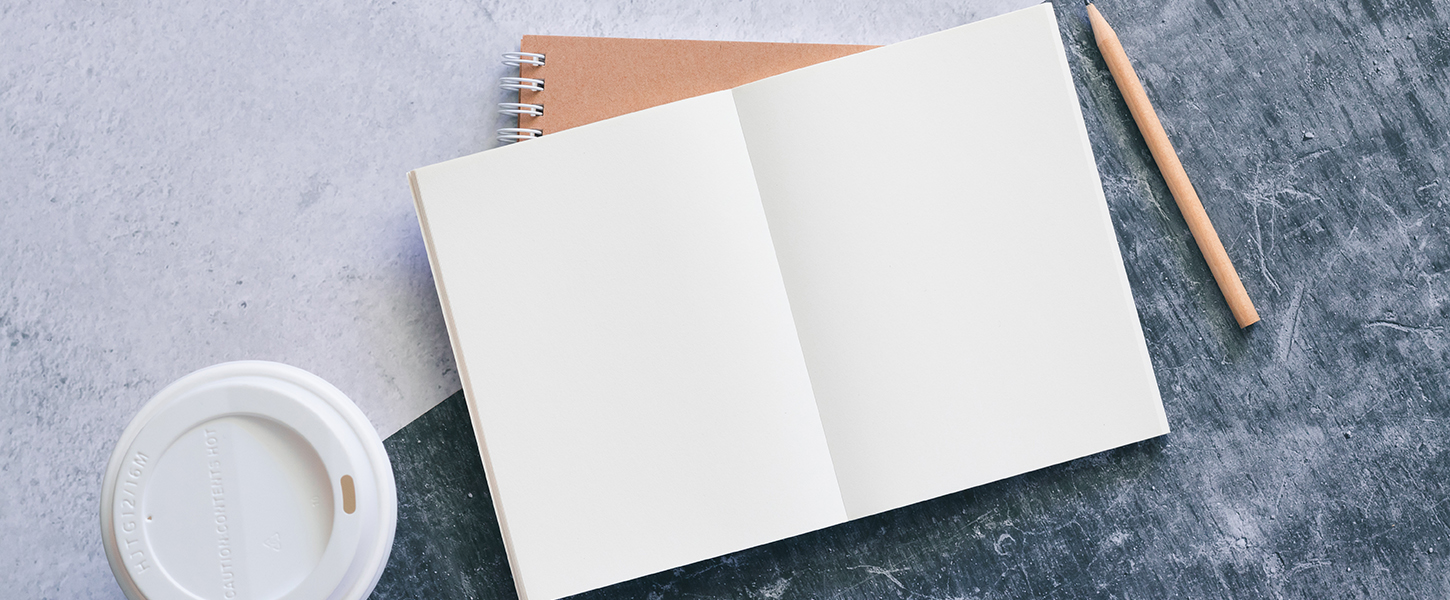





この記事へのコメントはありません。